稲垣えみ子が超シンプルライフをはじめたきっかけは原発事故だったんだ。
「寂しい生活」
稲垣えみ子著 東洋経済新報社
著者の本をほとんど読んできて、この本で、その著者のシンプルライフのはじまりをようやく詳細に知ることになった。
現在(2024年時点)出版されている9冊の単行本のうち、すでに7冊を読んで、読書エッセイを書いている。
そんな私にとって、この本は、本当はもっと早く読むべき本だったのだろう、と思う。ここからはじめれば、他の本に出てくるエピソードも、既知のこととしてもっと分かりやすかったかもしれない。
いや、今こうして(ある意味)読み返すことで「ああ、あそこのあれ、このことだったのか」などとピンときて逆に面白い、とも言える。
さてさて、言わずと知れたアフロえみ子の超節約生活。そのはじまりは、東日本大震災のときの原発事故だったのだ。すなわち、事故後の節電。
そうだったなぁ、とこの本を読みながら思い出した。計画停電なんてありましたね。
その上、節電しろと言われても、なにをどう節電したらいいのやら。そもそも節電してるし、などと思ったりもした。でも、稲垣の節電ぶりは、普通に暮らしていたらおそらく誰も真似できない。だって電気代が月150円代って……。
福島第一原発が水素爆発した映像を見て、新聞記者の人たちも唖然としたようだ。私もはっきりと覚えているが、日本テレビのアナウンサーがその映像とともに爆発について伝えながら、その表情がこわばっていた。テレビ朝日の玉川徹は、周囲の報道スタッフたちが東京から逃げ出した、とどこかに書いていた。自分も避難をすすめられたが、ジャーナリストの本分を果たそうと留まる覚悟を決めたということだった。
それほど重大な事故だったのだ。今こうして生きているのは奇跡なのかもしれない。
そういえば、エスカレーターも止まっていたり、駅もスーパーマーケットも暗かったりってこともありましたね。今はすっかり震災以前の生活に戻っていて、そんなこともこの本を読むまで忘れていたほどだ(だめですね)。
震災でもCOVID19でも、そして政治でも、振り返って検討するという作業は大事なのかもしれない。流れるままにしていては、忘れるだけだ。それを好都合と考える一定の人間たちはいるけれど。
稲垣は「個人的脱原発計画」を思い立つ。
関西電力供給の電力の半分は福井の原発から来ている。この快適な暮らしを問い直さなければならない。そもそも著者は「電気じゃぶじゃぶ」の生活をしていなかった。にもかかわらず、この原発分の電気、すなわち自分の使っている電気の半分を減らしたい、と考える。さて、乾いた雑巾をどう絞ればいいのか。こまめに電気を消し、プラグを抜き……などしたが、なんと、電気代が微妙に増えていたりする。
そしてついに、全てのコンセントからプラグを抜いた、冷蔵庫を除いて。家も夜は暗闇の生活。
さらについに、ルビコン川を渡る稲垣。すなわち、家電を捨てる。
まず、掃除機。ほうきとちりとりと雑巾で十分に掃除はできる。
実は時計代わりに使っていた電子レンジを捨てる。
エアコンも必要ない。冬は寒いけど、湯たんぽがすばらしく役立つそうだ。
いろいろあって、冷蔵庫ともさよならする。
家電らとの決別までの物語、面白いのでぜひお読みください。
オール電化のマンションに誤って引っ越してしまった顛末も痛快です。
私の場合は、家電を捨てる、あるいは使用しないで生活することはできない。エアコン、炊飯器からドライヤーまで。テレビも見るし、部屋の明かりも点ける。老眼なんで明るくないと文字が読めない。
稲垣は銭湯に通っているそうだが、その料金と電気・ガス・水道代とどちらが金額的には安いのだろう、とちょっと思ってしまう。そうそう、ガスの契約はしていないらしい。カセットコンロを使っている。金額ではなく、いかにエネルギーを使用しないで暮らすか、なのかな。
日本の夏の湿度は半端ない。私はエアコンなしには生きていけない。疲れ切って身体を壊してしまうだろう、と思われる。そもそも酷暑にじっと耐える生活なんて、そんな毎日は楽しくない。暑さと湿気が苦手な私は、夏は毎年北欧へ避難しようと考えていた。が、どこなら快適なんだろう、気候危機の現在は…。
とはいえ、地震やその他の災害などで、文明の利器が使えなくなったとき、そのときは超質素生活を実践しなければならない、という覚悟を常に意識するようにはしている。そのときすることになるであろう生活の工夫のためにも、著者の超シンプルライフはとても参考になる。実践面だけではなく、精神面でもたいへん教訓になる。
本の終わりのほうに、こんな一節がある。
家電とはそもそも、女性の負担を減らすためのものだったのではないか?
家電が登場したことで女性の社会進出も進んだのではないか?すなわち家電は女性を解放したのではないか?
その家電を否定して暮らすということは、どうなのか?
なるほど。確かにそうだ。
(P235)
ちょうど私も、この読書をしつつ、同じことを思っていたのだった。どうなの?と。そうしたら書いてあったので、そうそう、と頷く、
いわゆる家事が楽になった、それは事実なのだ。
ところが、家電がどんどん発展して複雑になっていくにつれ、実は面倒なことが増えていっているのではないか。家電の掃除やメンテナンスだって大変だ。え?もしかして家事が増えた?その通りのようだ。
「家電を手放したら、家事が減った」と稲垣は書いている。
家電に限らず、モノが増えるということは、面倒が増えるということだ。
先日、家を紹介するテレビ番組を観ていたのだが「ここにはたくさん食料をストックしておけて便利ですよ」と売り手側がアピールしていたキッチン横のけっこう大きな棚スペース。私は思わず、わぁ掃除が増える、とテレビに向かって言っていた。
加えて、大量のモノを持たなければ広い家(スペース)も必要ないわけなので。
稲垣は、家電を捨てたことで、「ああ私の人生ってこんなもんで終わっていくのかと寂しく思っていたこの自分のなかに、まだまだ眠っていた力があった」ことに気づく。それは、「なんでもかんでもお金やモノで解決しようとしていたら永遠に気づかなかった力に違いない」と。家電に頼っていたことは、家電でなくてもできる。
自分にもこんなことできるんじゃん、と思うことが、私も老年期に入って思うことが多い。若い頃はやっぱり、欲しい欲しい、だったんだろうな。
「電通戦略十訓」というものがあるそうだ。「電通」とは日本最大の広告代理店。この標語は1970年代につくられたのだとか。ちょっと怖い。
もっと使わせろ
捨てさせろ
無駄遣いさせろ
季節を忘れさせろ
贈り物をさせろ
組み合わせで買わせろ
きっかけを投じろ
流行遅れにさせろ
気安く買わせろ
混乱をつくり出せ
(P252〜253)
人が生きていくのに必要なものなんて、本当はそんなに多くない。でもそれでは、みんなが必要なものを手に入れてしまったらものが売れなくなってしまう。それでは困る。だからこそ、人々に「まだまだ足りない」と際限なく思わせ続けなければならない。
(P252)
「資本主義の次に来る世界」(ジェイソン・ヒッケル著/東洋経済新報社)に次ように書かれている。少し長くなるが、稲垣の著書と通底するので引用させていただく。
成長志向のシステムは往々にして、人間の要求をあえて満たそうとせず、要求を持続させようとする。(略)
この傾向が最も明らかなのは計画的陳腐化という慣習である。売上をのばしたくてたまらない企業は、比較的短期間で故障して買い替えが必要になる製品を作ろうする。(略)
冷蔵庫、洗濯機、食洗機、電子レンジといった家電製品を例にとってみよう。メーカーはこうした製品の平均寿命が7年以下に落ちたことを認めている。しかし、「壊れる」のは、システム全体が故障するからではなく、内蔵された小さな電気部品が壊れるからだ。それらは容易にかつ低コストで、もっと長持ちするように設計できるはずなのだが。(略)多くの場合、修理できないように設計されている。結局、理不尽にも消費者は数年ごとに、まだ十分使える金属やプラスチックの大きな塊を捨てるはめになるのだ。
(P212〜213)
そういえば、私が30歳を過ぎた辺りから、物の値段が下がると同時に、製品が壊れやすくなったように感じた。まことしやかに周辺の人々も、5年で壊れるようにつくられてるんだ、と言っていた。そして、修理するより買ったほうが安い、というのが消費者の常識のようになっていった、と思う。実際そうなので、消費者は買うしかない。
今さらですが、本当だったんだ。
「資本主義の次に来る世界」の目次は、「第1部 多い方が貧しい」「第2部 少ないほうが豊か」となっている。
稲垣が、超ミニマム生活を通じて確認してきたことと一致している。「寂しい生活」の第5章は「所有という貧しさ」である。
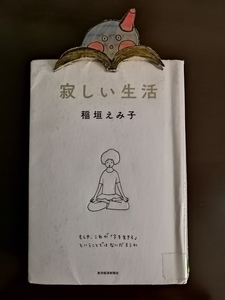
私の独断と偏見で抜粋した「寂しい生活」からの稲垣えみ子名言集。
ご参考までに。話題の流れもあるので、できれば読書をおすすめします。
何かを手に入れることは、実は何かを失うことであったのかもしれない。
(P63)
「あれば便利」は、いつの間にか「あって当たり前」になっていく。
(P69)
自分の目で見て、自分の頭で考えてやってみるということ。もしやそのことを、今の世の中は「不便」と呼んでいるんじゃないだろうか。
だとすれば、不便って「生きる」ってことです。
(P73)
この世は実にこんがらがっている。ただただ便利な暮らしを求めただけなのに、いつの間にか大きなものに絡め取られて身動きが取れなくなっていたりする。
いったい何が悪かったのだろうか?
(P117)
冷蔵庫には「いつか」の夢がいっぱい詰まっているのだ。そう、冷蔵庫とは、「いつかの箱」であり「夢の箱」なのである。
ところが冷蔵庫をやめてしまったら、身もふたもない現実を生きなければならなくなった。そして、その現実を生きるのに必要なものは驚くほど少なかったのだ。一回の買い物で使うお金が500円を超えることはほとんどなくなった。
(略)
これまでカゴいっぱいの何を買っていたんだろう?
(P132〜133)
人の悩みのほとんどは、過ぎ去った過去を悔いたり、まだ来ぬ未来を思って心配したり悩んだりすることそのものにあるというのだ。
ナルホド!そりゃまさに私のことである。
(P134)
(略)つまらない日々は、一方で心安らぐ日々なのである。
(略)余分な食材の一切ない台所は実にすっきりしている。
妙な話だが、私は冷蔵庫をなくして以来、ものを腐らせるということがほとんどなくなった。必要十分なものしか買わないから、いや買えないからである。
(P136)
しつこいようだが、人が食べられる量には所詮は限界がある。だからその多くは廃棄されることになる。簡単に言えば「食の買い捨て文化」を冷蔵庫が作り出したのではないだろうか。大量生産・大量廃棄。これが経済を回してきたのである。
(P143)
冷蔵庫の中には、買いたいという欲と、食べたいという欲がバンバンに詰まっている。人の欲はとどまることを知らず、その食べ物の多くは実際には食べられることはない。もはやそれは食べ物ではない「何か」なのだ。
(P144)
こんな状況では、(略)「生きていく」こととはなんなのかが誰にもわからなくなっている。「欲」と「欲じゃないこと」の境目がグズグズになっている。そんな中では、自分にとって「本当に必要なこと」はどんどんわからなくなり、人はぼんやりとした欲望に支配される。ただただ失うことだけをやみくもに恐れるようになるのである。
それが、今の世の中における「不安」の正体なのではないか。
(P145〜146)
不安がなくなったら、ストレスもなくなった。
ストレスがなくなったら、欲もなくなったのである。
欲ってどうやら、慰めるための甘いお菓子みたいなものだったんだな。
(P147)
(略)可能性を広げることが豊かさなのだと信じて生きてきたのである。
しかし、それは本当に豊かさだったのだろか。可能性を広げると言いながら、実際には欲を暴走させて不満を背負いこんできただけではなかったのだろうか。
可能性を閉じて生きる。
私はその可能性にかけてみようと思っているのである。
(P153)
諦めないということ。小さなことでもトライするということ。
節電も人生も果てしない壁との戦いである。
(P187)
その欲望のメガネをいったん外してしまうと、そこにはまさかのまったく違う光景が広がっていたのであった。
イケてない巨大なプラスチック製品の群れを高いお金を払って買い、さらにその家賃までせっせと負担している自分がそこにいたのである。
(P202)
(略)地位でも肩書きでも財産でもなく、その人の「振る舞い」だけが人の価値を決めるのである。
(P207)
我々はもはや、差がなければ豊かさを感じることができなくなっている。そしてそれは、何かの罠みたいなもんじゃないだろうか。
(略)
そんな競争に、果たしてゴールがあるのだろうか?もしかしてそのゴールが原発事故だったのではないか?自分さえよければ誰かを踏み台にしてもよいという考え方が原発事故を生み出したのは偶然でもなんでもない。
(P211〜212)
本だって何も所有することはない。読み終わったら古本屋へ売ったり図書館へ寄付する。読みたくなったらまた買えばいい。つまりはね、あなたはすでに家の外に巨大な書斎を持っているというわけです。
(P214)
えっと、これはちょっと賛同できない。家の空間を確保するために本を家に置くな、ということだと思うのだが。いや、それも一理あるし、私も図書館を自分の本棚だと思おうと考えたことがある。が、読み終わったら売ればいい、読みたくなったらまた買えばいい、はちょっと私とは意見が違うかも。
本についてはまた別の機会に。