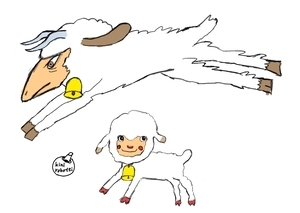NHKで放送されるというので、録画して視聴した。
どんな物語なのか、予備知識はゼロだった。
「チリンの鈴」1978年日本
原作絵本・脚本/やなせたかし 監督/畑正美
制作プロダクション/サンリオ 制作/辻信太郎
そして、これを最後まで観て、ふと気づいた。
これは…。
ある牧場で生まれた子羊。ある日、谷底に落ちてしまった。助けられたのち、どこに行ってもすぐにわかるようにと、母親が子羊の首に鈴をつける。そこから「チリン」と呼ばれる。
狼「ウォー」に、常に用心していた羊たち。しかしあるときウォーが、羊たちが平和に暮らす牧場を襲う。チリンの母親がチリンを庇って、ウォーに殺されてしまう。
チリンの心には悲しみと怒りがある。しばらくして、チリンはウォーに会うために険しい岩山へ向かう。
復讐を試みるが、勝てるはずもない。
「なぜ弱い者が死んでいくのか」
チリンは、強くなりたいとウォーに弟子入りする。3年間の激しい修行ののち、チリンの姿には、やさしくおとなしい羊の面影がなくなっていた。そこにいたのは、鋭く大きな角を持つ荒々しい獣だった。
それでも、チリンはなかなか復讐をはたせない。次第に、ウォーへの愛情のようなものさえ芽生えていく。そしてウォーとチリンの蛮行は、周囲に知られていく。
そんなある日、ウォーが、ある牧場の襲撃計画をチリンに持ちかける。そこは、チリンの生まれ故郷だった。
羊小屋へと勢いよく突入していくチリン。もちろん、誰もこの獣がチリンだとは気づかない。
逃げ遅れた子羊が、弱々しく鳴いて助けを求めている。そこへ母羊がやってきて子羊をかばう。その様子は、幼いあの日、ウォーからチリンを守ってくれた母の姿と同じだった。チリンは戸惑う。チリンには羊たちを殺すことはできなかった。
そんなチリンを見て苛立ったウォーが羊たちに襲いかかる。チリンは思わずウォーに立ち向かってしまった。
チリンの心に、あの幼い日の記憶と復讐心が蘇る。
そして、チリンはウォーへの復讐を果たす。しかしウォーは満足げに死んでいく。
羊たちを助けることになったチリンだったが、羊たちはチリンを受け入れようとはしない。チリンにもう居場所はなかった…。
なんとも悲しい物語である。
でもすぐに分かりました。これ、「あんぱん」のあのシーンだ。
「あんぱん」NHK朝ドラ2025年前期
脚本/中園ミホ
出演/今田美桜 北村匠海 他
第12週「逆転しない正義」。戦時中、中国でのことだ。崇(北村匠海)の幼馴染である岩男(濱尾ノリタカ)が、殺されてしまった。銃を撃ったのは、中国人の男の子リンだった(名前からしても「チリン」だね)。
岩男は両親のいないリンの世話をし、仲良くしていたのだ。なのにどうして?
死に際に岩男は崇に言う。「覚悟していた、リンはようやった。これでいい。リンは親のかたきを討ったんだ」と。
上等兵の八木(妻夫木聡)が岩男を撃った敵を追っていくと、草かげにリンがいて、こちらに銃を向けていた。
八木は、リンから聞いた話を崇に語って聞かせる。
リンの村が攻撃目標となったとき、リンの両親は射殺された。母親はリンを庇い、リンの体に覆いかぶさって死んだ。母親を撃った日本兵をリンは見ていた。それが岩男だった。
リンは、「父さんの形見の銃でかたきをとった。でも、僕の胸はちっとも晴れない。イワオはぼくのやさしい先生でした」そう話した。
八木 お前は、リンが憎いか?幼馴染のかたきを討ちたいか?
崇 わかりません。
八木 柳井、まえに戦場で生き残るには卑怯者になることだと言ったのを覚えているか。卑怯者は忘れることができる。だが、卑怯者でないやつは、決して忘れられない。お前はどっちだ。…どっちなんだ!
崇は八木の前では何も答えられなかった。
そして、「わかりません」と、ひとり呟く。
このリンの体験、チリンと全く同じ。母親がリン(チリン)に覆いかぶさってリン(チリン)を助けた。「覚悟していた、これでいい」と岩男が死に際に言ったように、チリンの角に刺された狼ウォーも同じことを言って死んでいった。
「僕の胸はちっとも晴れない。イワオはぼくのやさしい先生でした」と言うリンの気持ちも、ウォーのことを父親のように感じていたチリンと同じだ。でも、それでも復讐した。
「チリンの鈴」は、なんとも救いがたい物語だ。やなせたかしは、作品に込めた思いを次のように言っている。
悪者は最初から最後まで完全に悪いわけではありません。
世の中にはある程度の悪がいつも必要なのです。
確かに、善の心だけを持っている人間は世界中探してもどこにもいないだろう。全く違う文化を持つどこか遠い宇宙の惑星ではそういうこともあるかもしれないが、そこはそこでまた別の課題があるに違いない、と思われる。善と同様、悪の心だけを持って生まれてきた人間はいないだろうし、そもそも悪の心を持ってこの世に生まれるということはない(ということになっている、悪魔を除いて)。
ただ私がちょっと思うのは、同じ状況になっても、チリンのようになる人とそうでない人がいるのではないか、ということだ(戦場でもそうだったかもしれない)。チリンは、どちらかというとやんちゃでひとりでどこへでも行ってしまうタイプ。おとなしく内向的な性質だったら、悲しくて悔しい気持ちは同じでも、復讐を思い立って殺害を実行するということがはたして可能だろうか。
チリンが変貌していく様子は、ダース・ベイダーを彷彿とさせる。
八木に「幼馴染のかたちを討ちたいか」と問われて、「わかりません」と崇は答えたわけだが、私もこのシーンを見ながら「分からない」と思った。
「かたきを討ちたくない」と答えれば、友人に失礼な気もするし、「かたきを討ちたい」と言えば、なんとも危険な人間ではないか?それでも江戸時代には、「仇討ち」という制度があったわけだが。
八木によれば、卑怯者であれば忘れられる。ゆえに、戦場でも傷ついたり、苦しんだりしなくて済む、ということだろう。逆に、卑怯者でない人は、忘れられないから苦しむ。リンは悲しかった、苦しかった、だから復讐してしまった…ということになる。
このなんとも矛盾する人間の感情は…複雑だ。
仏教やキリスト教だったら、恨んだり仕返ししたりすることは良くない心だ。人間はそこで成長していく。やなせの言う「悪者は最初から最後まで完全に悪いわけではありません。世の中にはある程度の悪がいつも必要なのです」は、そういう意味なのか?
加えてもうひとつ。
八木の問い掛けは、復讐というものは繰り返されて順繰り続いていくという可能性を十分に持っているものだ、ということを示唆していないか?私はこのシーンを観ながら、そう感じた。
そして、崇が「わかりません」と答えのは、誠実な反応だったのではないか、と思った。八木も答えが欲しかったのかもしれない。自分を安心させてくれる答えを、求めていたのかもしれない。崇だったら何か答えを持っているかもしれない、という期待もあったかもしれない。
「チリンの鈴」で表現されたメタファーを、「あんぱん」のこのようなシーンに反映させるとは、脚本家・中園ミホの並々ならぬ思いが伝わってくる。